前回の解説ではプレゼンとは何かをお伝えしました。
まだご覧になっていない方はこちら
今回はプレゼンの準備パートです。
これからテーマを決めますが、その前にまず、プレゼン相手は誰かを明確にしておきましょう。
そしてテーマを決めながら目標設定を行いましょう。
ゴールを明確にしておくことでその後の作業が進めやすくなります。
テーマ決めの前に
プレゼンを行うとなった場合、聴衆が誰なのかその時点で決まっていると思います。
病棟看護師なのか、透析スタッフなのか、臨床工学技士なのか、はたまた医師や他のコメディカルなのか。
相手が決まっているとテーマ選びの選択肢が狭まるとともに、今後作成するプレゼン資料の内容や目標設定もスムーズに進みます。
病棟スタッフ相手に透析の穿刺方法のプレゼンはしませんし、また、新人看護師相手なら輸液ポンプの作動原理の説明はある程度省く必要があります。
こういった観点から、まずはプレゼン相手を設定してからテーマ選びを始めましょう。
テーマを決める
プレゼン相手を明確にできたところで、さっそくテーマを決めていきます。
皆さんはテーマをどのように決めていますか?
すでにテーマが与えられていたり、目的が定まっている場合を除き、多くは自ら設定しなければなりません。

もともとテーマ決めに時間かかってたけど
前回学んだプレゼンの目的を考えると、さらにテーマ決めが難しくなったなあ
大丈夫、まずは深く考えず、ざっくりとテーマを選定していきましょう。
得意分野から
- 興味があり、調べたいこと
- 知識があり、共有したいこと
一番選びやすく、書きやすい分野です。
プレゼンに慣れていなかったり、苦手意識を持っていたり、準備期間があまりない場合は得意分野から選定すると時間を有効に使えるので、いいかもしれません。
ただし、目的をしっかりと定めないとただのスピーチになってしまうので注意が必要です。

うぅ、耳が痛い・・・
日々の業務から
- 疑問に思うこと
- 業務改善したいこと
日々の業務で疑問に思うことを調べたり、先輩や医師から教わったことを忘れないようメモしたりしますよね。
そういったことを深堀りして、まとめてプレゼンする方法です。
または、業務効率が悪く、改善してほしい場合だったり、こうした方がいい!というような日々の業務改善提案にプレゼンを利用する方法です。
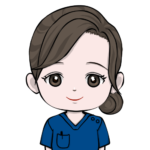
私は穿刺部の消毒薬の問題点を指摘して0.2%CHG綿を0.5%CHG綿へ変更してもらったことがあるよ
苦手分野から
- 苦手だからこそ学習
- 失敗から成功へのSuccessを
- 他の人(後輩や同僚)への助言
苦手なことをそのままにする人もいますが、苦手だからと言ってもその業務に従事しないという選択肢は選べないですよね。
調べて学んだことをまとめてプレゼンしましょう。
プレゼンの準備を通して、繰り返し本を読んだり、まとめたり、説明したりするので、知識が身に付きやすいのが特徴です。
一石二鳥ですね。
ただ、苦手な分野の学習をしながらの作業になるので苦痛かもしれませんし、それなりに時間もかかります。
こちらの場合も、調べたことをまとめて発表して終わりにならないように注意が必要です。
目的から
- 医療機器安全管理研修
- 新規採用医療機器の取り扱い研修
- 新人看護師研修
こちらはプレゼンの目的がすでに決まっているパターンですね。
医療機器安全管理研修
医療機器安全管理のための研修は年に2回程度行うことを義務付けられています。
多くの施設でCEが任されているのではないでしょうか?
毎年2回ずつ行うのでネタも尽きそうなものですが、医療材料もほとんどの場合が添付文書上”医療機器”ですので、いくらでもあります。
PMDA情報から選択するのもありですね。
※PMDAとは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA;Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)のことで、医薬品や医療機器の安全情報などを集約し、発信している機関です。
新規採用医療機器の取り扱い研修
新規医療機器の取り扱い研修はメーカーにお願いすることもあるかと思いますが、できればCE自身で行いたいですね。
メーカーは機器の操作方法はわかりますが、臨床のことはわからないので、実際に使用する際の注意点や、使用環境などがわかるCEで行いましょう。
新人看護師研修
個人的考えですが、新人看護師研修では、まずCEとは何か、どうゆうことをしてくれる存在なのかをぜひ伝えていただきたいと思います。
その後、医療機器(おそらく一番最初は輸液ポンプ、シリンジポンプだと思いますが)の取り扱い研修に入ると、CEの存在を早く認識してもらえるし、大事になる前に連絡してもらえるようになります。
余談ですが、院内におけるCEの立場はまだ低く、活躍の場を広げられていません。
様々な場面でCEの業務をアピールしましょう。地道な活動がいずれ実を結びます。
目標設定
プレゼンのテーマも大まかに決まり、いよいよ目標、ゴール設定を行います。
何度も言いますが、プレゼンは相手の行動を促すことが成功条件です。
プレゼンを通して相手に何を伝えたいのか、今後どうしてほしいかを設定します。
- 目的:何のために行うのか
- 伝えたいこと
- 聴衆が知りたいこと
目標を設定すると、おのずとテーマもざっくりしたものからより明確になると思います。
例えば・・・
プレゼンの場:医療機器安全管理研修
プレゼン相手:院内の医療従事者全て
ざっくりテーマ:人工呼吸器
目標:人工呼吸器に対する苦手意識をなくす
もしプレゼン相手が日常的に人工呼吸器に携わっている看護師の場合は、目標をもう少し上げて「アラーム対応が臨機応変にできる」や、「呼吸器の設定が理解できる」などにしてもいいですね。
プレゼン相手にリハビリの職員(PT,OT,ST)などが多い場合は呼吸リハに絡めた内容を入れてもいいかもしれません。
人工呼吸器なんて全く触らないけど、人工呼吸器装着患者の口腔ケアにはいる歯科衛生士がプレゼン相手になることもあるでしょう。
そんなときは内容をより簡単に、かつコンパクトにまとめる必要があります。
プレゼン相手や求められる情報を認識したうえで、目標を設定しましょう。
まとめ
テーマ決めのお手伝いになったでしょうか?
- まずプレゼン相手を明確にする
- 目標設定を行うことでテーマがまとまる
- 目標設定を行うことでこの後の作業が進めやすくなる
プレゼンに自信のない人は、まず自分の得意な分野からテーマをえらんでみましょう。
書きやすいテーマにするとその後がスムーズに進み、その成功体験があなたの今後にいい影響を与えてくれます。
次回からはプレゼンの資料作成について解説していきます。お楽しみに!

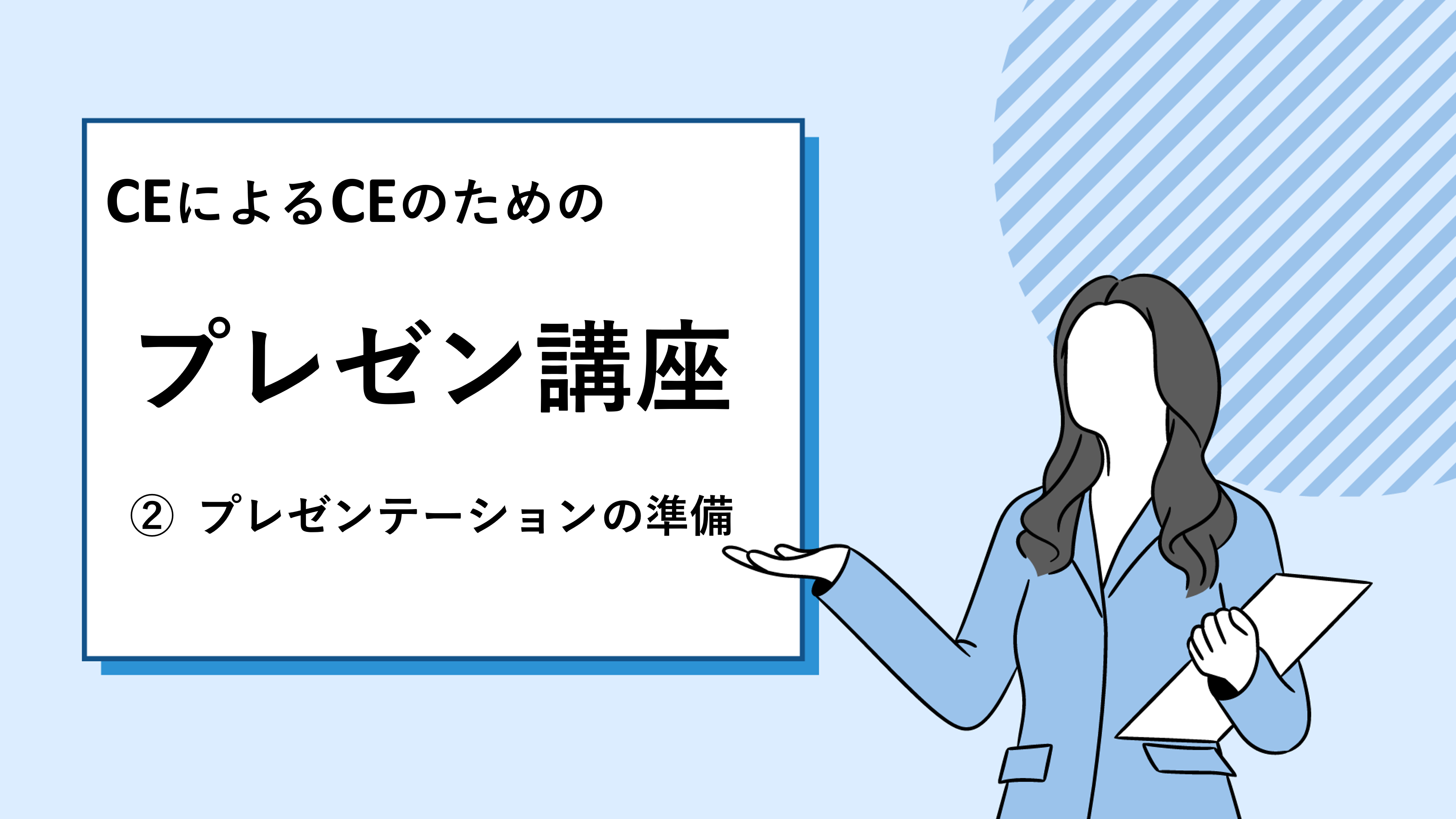


コメント