プレゼンのテーマ、目標も定まったのでいよいよ資料作成に取り掛かります。
何度も言いますが、プレゼンは相手の行動を促すことが成功条件です。
いかにわかりやすい資料を作成するか、相手の記憶に残るものにするかが重要になってきます。
これからプレゼンの構成を説明していきますが、CEが行う1対他人数相手のプレゼンは基本3部構成が重要になりますので、しっかりマスターしてください。
3種類の基本構成
ネットで検索すると、よく言われるのが次に示す3種類の構成法です。
- 3部構成
- PREP法
- DESC法
それぞれにそれぞれの良さがあるので、自分に合った方法やプレゼン内容によって使い分けましょう。
3部構成
最もオーソドックスな方法で、皆さんが実際に行ったプレゼンも近い形ではないでしょうか。

僕も学生の頃にやったプレゼンはまさに序論、各論、結論の構成でした。
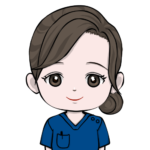
私も基本的に3部構成でプレゼンを作成するよ。
改めて説明すると次のようになります。
- 序論
- 各論
- 結論
序論
学生の頃はこの序論部分で「なぜこのテーマをえらんだか?」を説明して導入するパターンをよく見ますね。
ちなみにうちの娘がはじめてやったプレゼンの資料作成で、学校から指導されたのはまさにこの導入方法でした。
我々はもう学生ではないので、もう少し違った方法で序論を述べられるといいですね。
例えば、もくじなどを使って研修内容の概要を伝えてみましょう。
これから始まるプレゼンに対して聴衆も聞く準備ができます。
研修の目的、目標などを合わせて示すと、聴衆もゴールがわかるので聞きやすく、意識に残りやすいです。
各論
本題の部分では、あなたが伝えたい部分と聴衆が知りたい部分の配分を間違えないようにすることがポイントです。
こちらの伝えたいことばかりの内容では聴衆は飽きてしまいます。相手の伝えたいことをくみ取り、内容を盛り込みましょう。
各論の展開としては概要から詳細へ、また、時系列を意識して伝えましょう。
例えば人工呼吸器の研修をする場合、いきなり人工呼吸器の話をしてもわからないことが多いです。
まず、呼吸生理をおさらいし、その後で人工呼吸器へ進むのがいいでしょう。
輸液ポンプの取り扱いなら、輸液ポンプを使用するかどうかの判断基準から、必要物品、セットの方法、開始方法、使用中のチェックポイント、アラーム対応、使用後の処理の順に説明するとわかりやすいですね。
また、他機種を同時に研修する場合は、混乱しやすいので1機種ごとに説明しましょう。
結論
全体を通して内容をまとめ、一番伝えたい言葉で締めくくりましょう。
また、導入部分で触れた内容を再び示し、目標達成できたか問うと聴衆のレスポンスで手ごたえが感じられるかもしれません。
PREP法
PREP法というのは、話す内容を示す英単語の頭文字を取ったものでプレップ法と呼ばれます。
PREP法
- Point:結論
- Reason:理由
- Example:具体例
- Point:結論
ビジネス会話や、ビジネス文書はこの構成でされていることがほとんどです。
この方法は論理的に話を進めることができるため、より説得力をもってプレゼンができるという特徴があります。
まず結論を提示するため、聴衆がより興味をもって話を聞いてくれ、プレゼンの波に乗りやすくプレゼンター側もやりやすい方法だと思います。
これはプレゼンうんぬんより、機器の新規購入申請だったり、故障・修理申請、オーバーホールなどの申請を事務方へ訴えるときなどに実際に利用している方が多いでしょう。
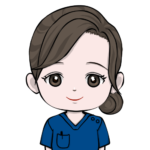
私は院内向けの文書や、事務方へ提出する申請書はPREP法で作成します。
DESC法
この方法は問題解決型と言われる方法です。
DESC法も話す内容を表す英単語の頭文字を取り、デスク法と呼ばれます。
DESC法
- Describe:描写
- Explain:説明
- Specify:提案
- Choose:選択する
この方法は相手に納得してもらいつつ、こちらの提案をのんでもらうために行う手法です。
まず状況を客観的に描写し、自分の考えを述べ、解決策を提案し、そして相手に選択してもらうという流れです。
1対1の場面で上司に業務改善提案などを上申する際に利用すると効果的だと思います。
まとめ
プレゼンの構成を3つ紹介しました。
先にもお伝えしましたが、ここでのプレゼンは1対他人数を想定して説明していくので、基本の3部構成で進めていきます。
次回からはスライドの作成方法について解説していきます。お楽しみに!

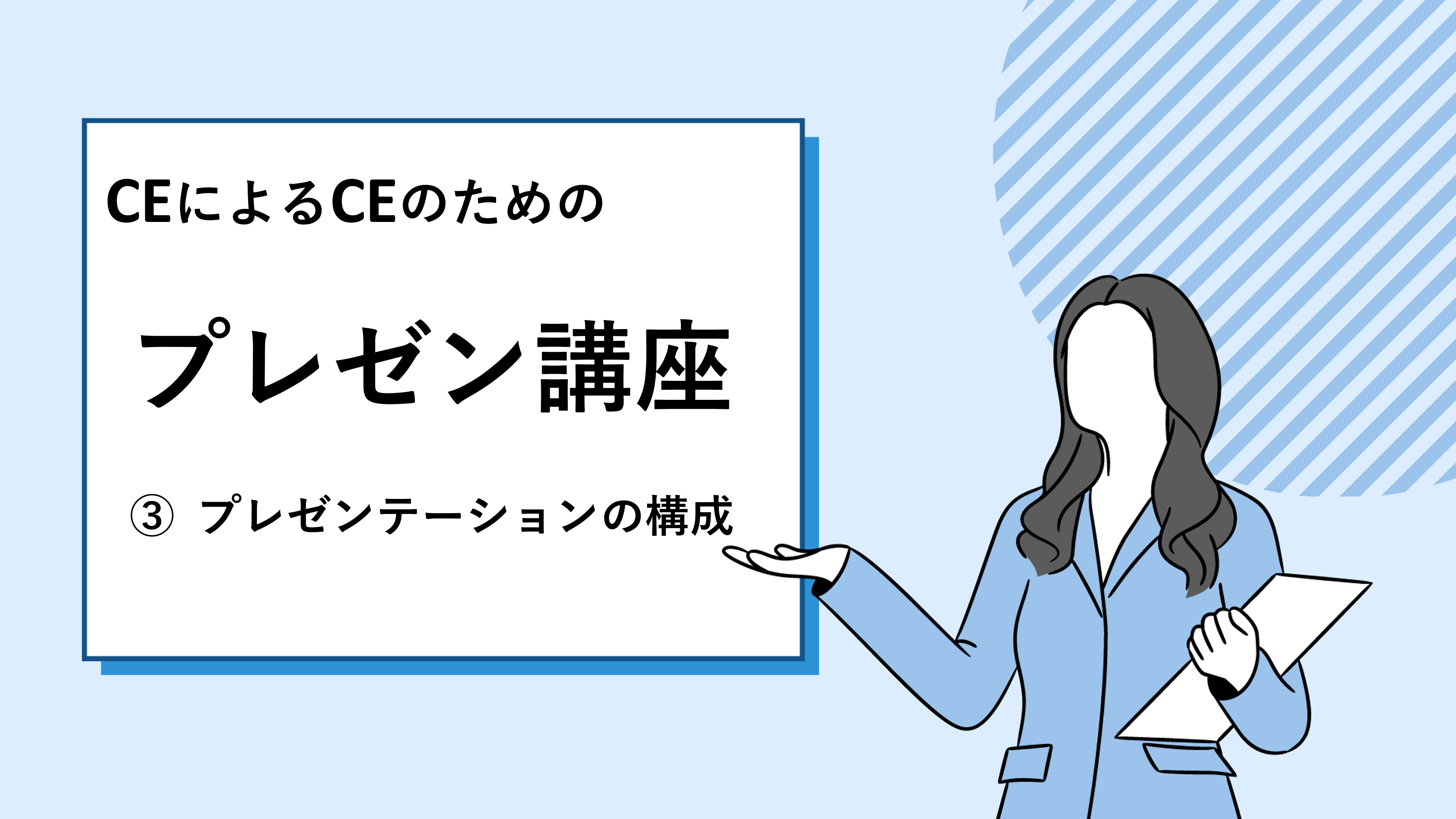


コメント